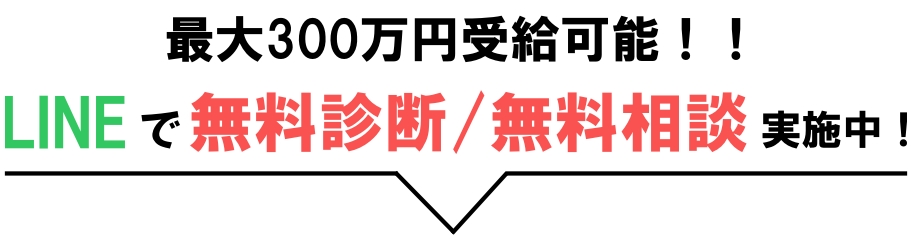元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 自分は何日間失業保険が受給できるか知りたい
- 失業保険を申し込むのを忘れていた!受給できる期間はある?
- 失業保険を受け取るために必要な書類は?
このようにお悩みではありませんか?
失業保険は退職理由や年齢ごとに受け取れる期間に決まりがあります。しかし、自分がどれくらいの金額を受け取れるのかわからない方も多いのではないでしょうか。



そこで、この記事では失業保険が受給できる期間を退職理由ごとに詳しく解説するのでぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!
失業保険を受給できる期間


失業保険を受給できる期間は退職理由や年齢によって異なります。ここでは以下3つの区分ごとに失業保険を受給できる期間を解説するので、参考にしてください。
- 一般の離職者
- 特定受給資格者や一部の特定理由離職者
- 就職困難者
一般の離職者が失業保険を受給できる期間
一般の離職者には転職や独立を目指した自己都合退職した方が該当します。一般の離職者の受給期間は全年齢で共通しており、他の区分に比べて受給できる期間が短いのが特徴です。
一般の離職者が受給できる期間は以下の通りです。
| 雇用保険の被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 受給できる期間 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
なお、一般の離職者は退職してから2ヶ月の給付制限があるため注意しましょう。
特定受給資格者や一部の特定理由離職者が失業保険を受給できる期間
特定受給資格者や一部の特定理由離職者には病気やケガだけでなく倒産や突然のリストラなど自分の意思に反して退職しなければならなかった方が該当します。年齢や雇用保険の被保険者期間によって給付期間は変動します。
特定受給資格者や一部の特定理由離職者が受給できる期間は以下の通りです。
| 離職時の年齢 | 雇用保険加入期間 | ||||
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
なお、特定受給資格者や一部の特定理由離職者は退職に相応の理由があると判断された場合、給付制限が取り払われることがあります。
就職困難者が失業保険を受給できる期間
就職困難者には障害や社会的な事情により就職が著しく難しいと判断される方が該当します。特定受給資格者や一部の特定理由離職者ほど厳格ではないものの、同じく年齢や雇用保険の被保険者期間によって受給できる期間は変動します。
| 離職時の年齢 | 雇用保険加入期間 | ||||
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
就職困難者は最大で1年間の失業保険が受給できます。可能な限り多く受給を受けるためにも、なるべく早くハローワークで申請するとよいでしょう。
失業保険が受給できる期間は原則1年以内


失業給付は受給可能な期間が設定されています。基本的には退職した翌日から1年間が受給期間で、受給期間を超えると給付日数が残っていても受給できません。
なお、所定の給付日数が330日の場合は、1年+30日になります。さらに、所定の給付日数が360日の場合は、1年+60日まで延長されます。
申請が遅れると受給できる金額も少なくなるため、退職後は速やかに手続きを進めましょう。
失業保険の受給期間延長の方法を紹介


病気やケガ、育児などによって退職後すぐに働けない方は失業保険の受給期間を延長できます。具体的な延長の手順は以下の通りです。
- ハローワークで受給期間延長申請書を受け取る
- 必要書類をハローワークに提出する
なお、郵送の場合は事前に郵送する旨をハローワークに伝えておきましょう。
ただし、受給期間の延長は本人が再び働けるようになるまで失業保険の給付を保留するものです。そのため、延長申請しても所定の給付日数が増えるわけではないため注意が必要です。
失業保険を受給するための条件を2つ紹介
失業保険を受給するための条件は主に以下の2つです。
失業保険を受給するための条件
- 失業状態でハローワークに求職の申し込みをしている
- 一定期間以上雇用保険の被保険者だった
失業保険は、失業状態であることが前提です。また、以前勤務していた際に一定期間雇用保険の被保険者だった必要があります。
失業状態でハローワークに求職の申し込みをしている
失業状態かつ求職意志と能力を持つ方のみが失業保険を受給できます。具体的には、ハローワークでの求職申し込みや求人への応募、面接への参加が必要です。
そのため、以下のように退職後すぐ働けないと判断できる方は失業保険の給付対象外となります。
- 病気やケガで入院している
- 妊娠や出産で働けない
- 仕事を辞めて専業主婦として家事に専念する
- 定年退職後にしばらく休養する
一定期間雇用保険の被保険者だった
失業保険を受け取るためには、雇用保険の被保険者期間が最低でも2年間のうちに合計で12ヶ月以上である必要があります。
被保険者期間とは、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の中で賃金支払いの基礎となった期間が11日以上または労働時間が80時間以上ある月です。
しかし、会社都合での退職や正当な理由がある場合は、被保険期間が軽減されることがあります。
なお、下記の記事では失業保険を受け取るための条件に付いてより詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
失業保険(失業手当)を受給できる条件は?手続きの方法や給付金額も紹介
失業保険の金額は?計算方法を解説
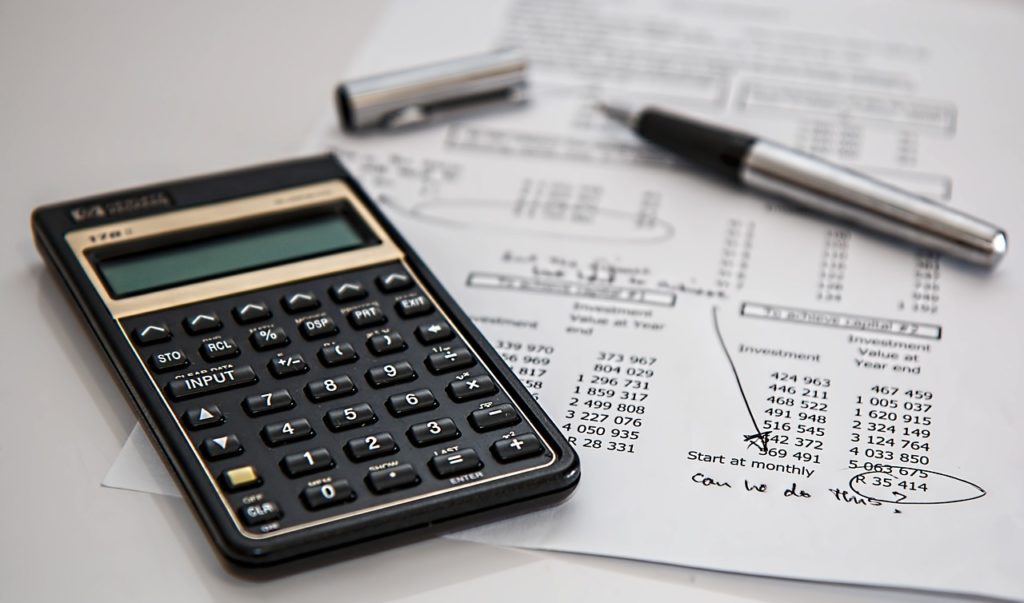
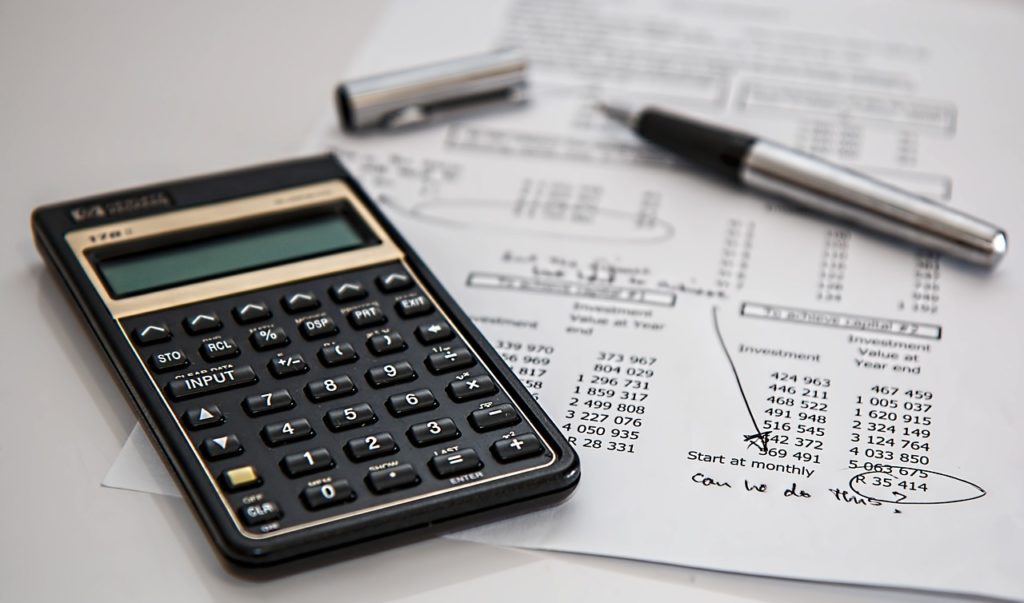
失業保険の支給金額は、以下の式で求められます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前半年の合計賃金÷180) × 給付率(50~80%)
過去6ヶ月間の総賃金を180で割った金額に給付率(50%から80%)を掛けることで、基本手当日額が算出されます。ただし、基本手当日額には上限額と下限額の範囲が設定されています。
基本手当日額の上限額は年齢によって以下のように変動します。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 6,835円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,595円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,355円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,177円 |
なお、下限額は年齢問わず2,125円です。
ただし、下限額は毎月の勤労統計の平均定期給与額の変動によって調整されるため、時期によって変動します。
失業保険はいつから受給できる?


失業保険の受給には、一般的に約2ヶ月かかります。
退職後には以前の勤務先から10日から2週間程度で離職票が届くため、持参してハローワークで求職の申し込みを行ってください。
ハローワークの職員と面談し、受給資格が決定された後は待機期間を経た後に雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取ります。
初回の失業認定日は受給資格が決定されてから約4週間後となるため、申請から受給までには早くても2ヶ月ほどかかってしまいます。
ただし、自分の意思に反する退職では受給までの期間が短くなる場合もあるので、まずは相談してみるとよいでしょう。
失業保険の申請に必要な書類
失業保険を申請するためには以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 本人の証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
書類が不足していると申請ができないため、手元にない書類があれば退職前から準備しておくのがおすすめです。
失業保険の期間に関するよくある質問
最後に、失業保険の期間に関するよくある質問を3つ紹介します。
失業保険の期間に関するよくある質問
- 失業保険は自己都合退職の後でもすぐもらえる?
- 失業保険の受給期間中にアルバイトをしても大丈夫?
- 失業保険は一度もらうともうもらえないの?
それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。
まとめ
この記事では、失業保険が受給できる期間について解説しました。失業保険は退職理由や年齢によって異なり、最大で360日間受給できます。
ただし、受給できる期間は原則1年以内です。退職してから1年を超えるとその分給付金も少なくなるので、注意しましょう。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!