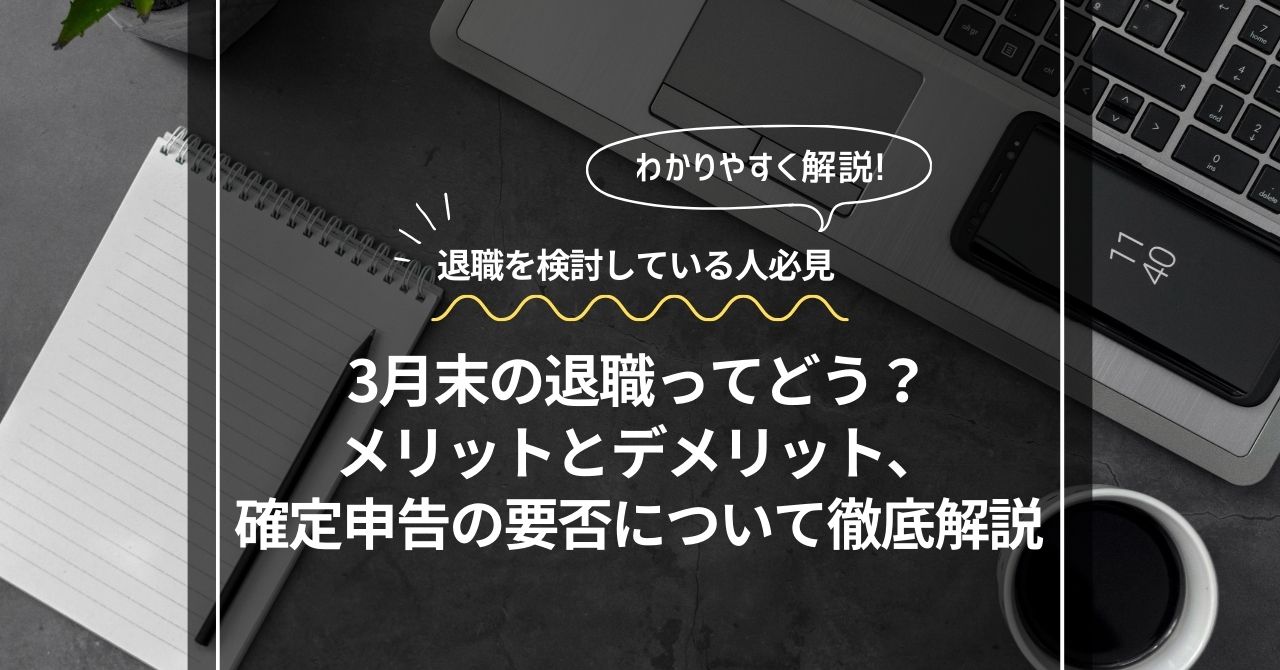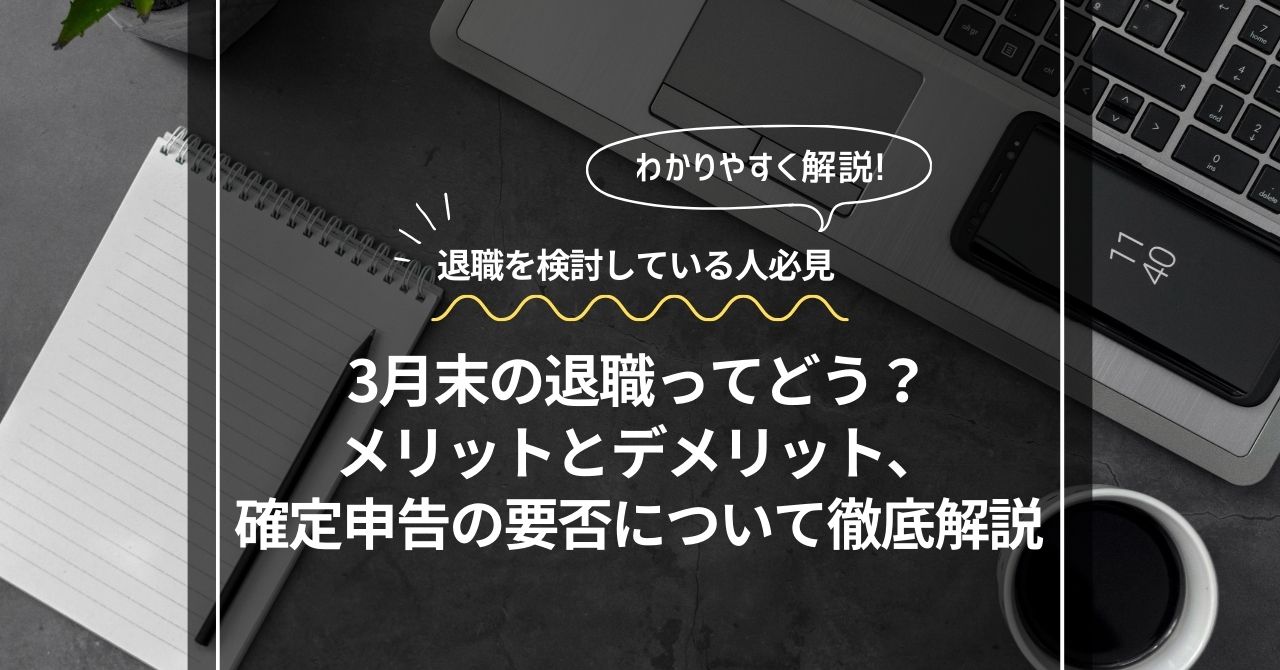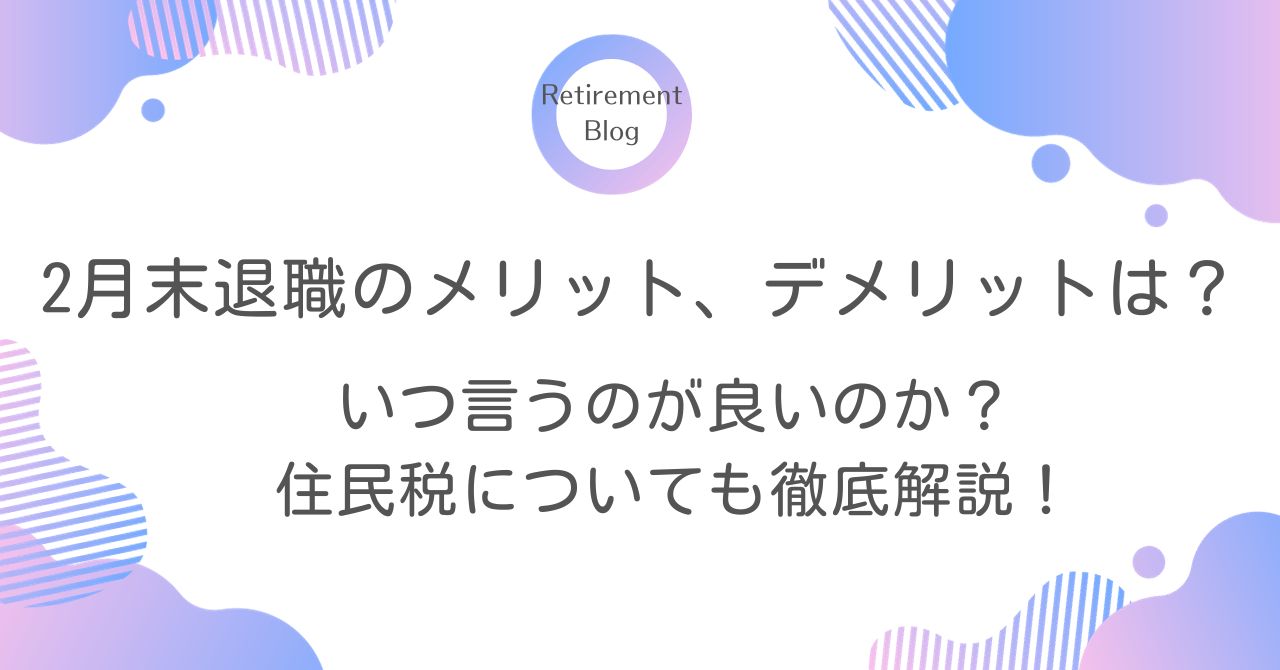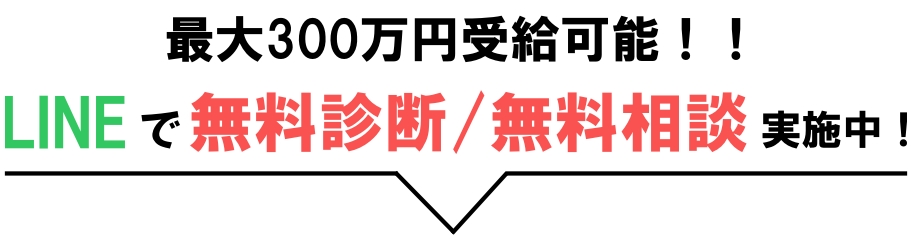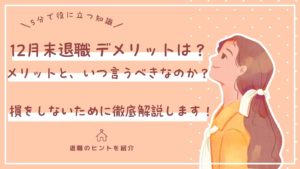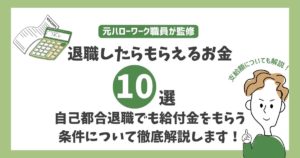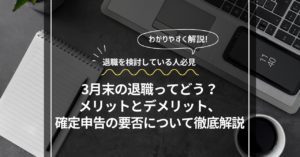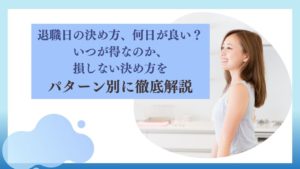元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員が解説いたします!
この記事は、こんな人にオススメです!
- 2月末に退職するんだけどデメリットとかってある?
- いつ上司に退職を伝えたらいいの?
- 転職活動への影響は?
- 住民税ってどうなるの?
- 退職日の決め方に悩んでいる。
2月末退職ということで、退職時期に上記の不安や疑問を持たれている方も少なからずいらっしゃると思います。
本記事では、2月末退職のメリット、デメリットや退職をすることをいつ言うのが良いのか?住民税について解説していきます。
2月末退職のデメリット
では実際に2月末退職にはどんなデメリットがあるのか?
実は2月末での退職のデメリットはそこまで多くありません。
2月末退職には以下のようなデメリットがあります。
- 給与の手取り額が減る
- 繁忙期だと退職しにくい
それぞれ具体的に解説していきます。
給与の手取り額が減る
給与の手取り額が減る理由が、住民税です。
1月1日から5月31日までに退職した場合、通常は退職月までの給与や退職金から、5月までの住民税がまとめて差し引かれます。
そのため、手取り額が減ってしまうということです。
しかし、退職月の給与と退職金の総額よりも住民税の差し引き額が多い場合、通常の控除方法から変更され、残りの差額を自ら納付する必要があります。
また、どちらにしても納めなければいけない住民税の為にマイナスになるという事ではありません。
繁忙期だと退職しにくい
決算を控えているため、3月末までは忙しくなる会社も多く、2月が繁忙期と重なると、なかなか退職相談に応じてくれないケースがあります。
トラブルを防ぐためにも、退職時期をずらした方が場合もあります。
以上のように、そこまでデメリットは多くありません。



キャリアアップを考えるとメリットの方が多く、むしろ転職活動をする上ではベストな時期だと言えます。
2月末退職のメリット
では実際に2月末退職にはどんなメリットがあるのか?
実は2月末での退職のメリットはデメリットよりも多くあります。
2月末退職には以下のようなメリットがあります。
- 求人数が増えている。
- 4月入社に向けて転職活動ができる。
- 賃貸の繫忙期のため生活環境を変えるタイミングとしても良い
- ボーナスをもらい終わっている。
- 確定申告が必要ない。
それぞれ具体的に解説していきます。
求人数の違い
求人数が増えるタイミングとして、2月、3月、9月、10月があげられます。
転職活動を始めるタイミングとしてはベストと言えます。
2月中に有給消化をして、その期間で転職活動を行えます。
求人の多い時期のため、自分に合った職場を見つけられる可能性があります。



ハローワークでも2月は求人が増えていた印象があります。
ボーナスをもらってちょうど良いタイミングなので、退職者も増える時期でした!
4月入社に向けて転職活動ができる。
4月1日に入社ができるとキリがよく仕事を始めることができます。
特に新入社員が増えるので、研修などもありしっかりと仕事を覚える時間をとれるのもかなり大きなメリットです。
未経験の仕事だった場合に、周りについていけずにすぐに退職してしまった、、、なんて話もよく聞きます。
2月で転職活動を終わらせて、4月入社からスタートが切れれば1ヶ月ゆっくりしてから仕事できるので気持ち的にもよいでしょう。
賃貸の繫忙期のため生活環境を変えるタイミングとしても良い
転職とセットになることが多いのが、引越しです。
1月~3月は、不動産賃貸業が繫忙期となっています。
この時期は、賃貸物件が多く出てくるので自分の希望に合う部屋を探せます。
少し妥協して、部屋を決めてしまった人は、転職と同時に転職先に近い部屋を見つけてみましょう!
ボーナスをもらい終わっている。
12月末や1月末退職となると、「この人はボーナスをもらって辞めた」と思われてしまうこともあります。
12月末退職だと場合によってはボーナスがもらえないこともあります。
しかし、2月末退職であればそのような心配は一切ありません。
会社が繫忙期とかでないのであれば円満退職しやすいのでオススメです!
確定申告が必要ない。
12月末に年末調整が終了しているので、確定申告をする必要がありません。
特に初めて行うとかなり負担が大きいのが、確定申告です。
自分でできなければ税理士などに依頼することになり費用が発生することもあります。
しかし、その年の12月末まで再就職をしていない場合は、翌年の確定申告は必要となってきますので注意してください。
退職を申し出るタイミング
2月末に退職をしたい場合、いつ退職の旨を伝えたら良いのでしょうか?
退職を伝えるタイミングは一般的に退職日の「1〜3カ月前」と言われています。
遅くとも退職する1ヶ月前までに伝えるようにしましょう。
2月末退職であれば、1月末までには伝えるようにしましょう。
12月末頃に伝えてしまうと少し印象が悪くなってしまうこともあるので、年明け落ち着いてから伝えるのがポイントです。
2月末退職の住民税について
2月末退職の場合は、住民税が5月分まで一括で給与から引かれてしまいます。
もう少し詳しく説明すると、
1月1日から5月31日に退職した場合、5月までの住民税が一括で天引きされます。
一方、6月1日から12月31日に退職した場合は、翌月以降に納付が予定されていた住民税については、普通徴収に切り替わるため、自分で納付する必要があります。



自分で納付は少し面倒なため、手取り額が減ることは仕方ないと思うしかありません。
2月末退職の確定申告について
2月末退職の場合は、確定申告はどうなるのか?
結論から申し上げますと、確定申告は不要です。
確定申告とは、わかりやすく説明すると
1年間の所得を計算して「正確な所得税」を計算をすることを言います。
しかし、従業員などの雇用されている人は、年末調整で1年間の所得が計算されます。
12月末日まで会社に席を置いていると翌年の確定申告をする必要がなくなります。
そのため、2月末であればその年の確定申告は必要ないです。



年間の所得が高額(2000万円以上)の場合は、確定申告が必要なので気をつけてください!
2月末退職の源泉徴収票について
2月末退職の場合に源泉徴収票ってもらえるのか?について説明します。
2月末退職の場合でも源泉徴収票は発行してもらいましょう。
再就職先に1月~2月までの収入を伝えなければいけませんので、源泉徴収票を発行しておき提出しましょう。
小さい会社だと言わないと発行してもらえないため、必ず退職を伝えるときに会社には「源泉徴収票を下さい。」と伝えましょう。



たったの2ヵ月分の給与でもしっかりと申告しないといけません。
よくある質問
2月末退職に関してよくある質問を挙げさせて頂きます。
2月末退職のよくある質問
- どうしても辞めさせてくれない時は?
- 他におすすめの退職月は?
- 何月入社がおすすめ?
どうしても辞めさせてくれない時は?
退職相談をしたのに辞めさせてくれない時は、退職代行サービスを活用して退職しましょう。職場に行く必要がなくなるので、余計なトラブルやストレスがなくなります。
どうしても退職を切り出せない時は、ぜひ退職代行サービスを活用しましょう。
他におすすめの退職月は?
2月末以外におすすめの退職月は、12月末と3月末になります。
12月末退職だと、冬のボーナスを受け取ってから退職することができ、転職もしやすい時期と言われています。
3月末退職だと、円満退職しやすいというメリットがあります。
何月入社がおすすめ?
おすすめの入社月は4月と10月と言われています。
採用ニーズが高まる時期であり、企業側の本気度も伝わってきます。
転職を成功させるには事前準備が必要となってきます。
「1人だと難しい。。」「忙しく時間がなかなか取れない。」といったお悩みを抱えられている方もいらっしゃると思います。転職活動をより効率よく進めたい方には「転職エージェント」の活用をおすすめします。
月末退職と月中退職の違い
まず始めに月末退職と月中退職の違いについてお伝え出来たらと思います。
実は退職する日によって、社会保険料の徴収額が変わってきます。
では月末退職だと、どのぐらい差が生じてくるのでしょうか?
社会保険とは
社会保険とは、公的な強制保険制度で、病気や怪我などの事故に備えられる制度で、勤務先の会社を介して加入します。
社会保険には、健康保険や介護保険、雇用保険などがあります。
社会保険料の計算方法
実際に各保険料の計算方法について解説していきます。
保険料は、従業員と事業主との折半になります。
健康保険料
健康保険料の計算方法は、「標準報酬月額×健康保険料率」で求められます。
例)標準報酬月額が25万円、健康保険料率が10.0%の場合、
「250,000円×10.0%」で25,000円が健康保険料になります。
健康保険料率は健康保険組合によって異なるので、予め確認をしておきましょう。
介護保険料
介護保険料の計算方法は、「標準報酬月額×介護保険料率」で求められます。
介護保険料率は1.82%(令和5年度)で決まっているので、
標準報酬月額を25万とした場合、
「250,000円×1.82%」で4,550円が介護保険料になります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料の計算方法は、「標準報酬月額×保険料率」で求められます。
保険料率は18.3%で固定されています。
例)標準報酬月額が25万円の場合、
「250,000円×18.3%」で45,750円が厚生年金保険料になります。
雇用保険料
雇用保険料の計算方法は、「賃金の総額×雇用保険料率」で求められます。
雇用保険料率は毎年見直しが入り、年によって異なります。
社会保険料の違い
月末退職と月中での退職だと、どのくらい差が出てくるのでしょうか?
月末退職の場合
月末に退職をすると、2ヵ月分の保険料が差し引かれます。
2月末に退職をすると、1月分と2月分の保険料が給与から差し引かれてしまいます。
保険料の負担は、被保険者資格の取得日の属する月から、喪失した日の属する月の前月までとなっております。ただし、喪失日が退職日の翌日と決まっているため、月末だと翌月1日が喪失日となります。
月中退職の場合
月中に退職をすると、退職をした月の保険料が給与から差し引かれません。
そのため国民保険料を全額自己負担で払うことになります。
一見すると月中退職の方がお得に見えますが、状況によっては月末退職の方が適している場合もあるので、月末と月中どちらがお得かは一概には言えません。
今後のスケジュールに合わせて計画的に退職日を設定しましょう。
2月末退職についてのまとめ
今回は2月末退職についてまとめさせて頂きました。
意外とデメリットが少なく、メリットも多く存在します。
ただし状況次第では、退職相談に応じてもらえなかったり、会社とのトラブルも起きて、上手く手続きが進めらないこともあります。
ポイントをしっかり把握した上で退職手続きを進めましょう。
他の月で退職を希望されている方、退職日の決め方については下記の記事のお読み下さい。